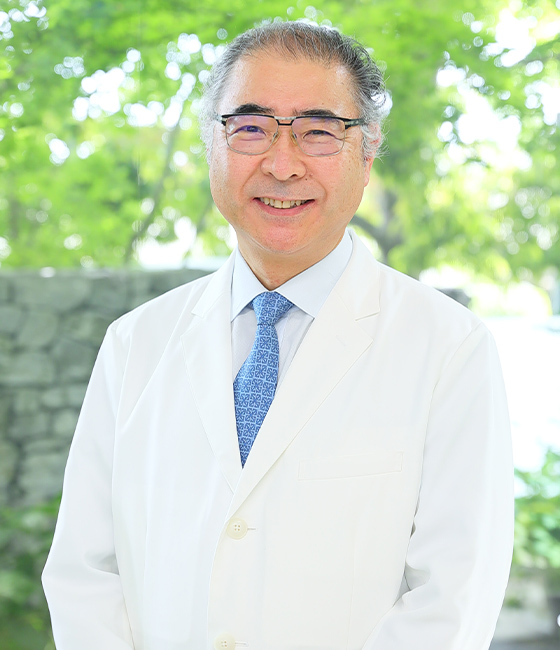「最近、なんとなく喉が渇く」「体がだるくて疲れやすい」なんて感じていませんか?
それは、糖尿病の初期症状かもしれません。
糖尿病は、初期段階ではほとんど症状が現れないことが多く、気づかないうちに進行してしまう「サイレント疾患」です。
しかし、症状が出始めると、喉の渇きや頻繁にトイレに行きたくなるなど、意外にも身体にわかりやすいサインが現れることもあります。
今回は、糖尿病の初期症状に焦点を当て、なぜそれが現れるのか、そしてどんなサインに気をつけるべきかを解説します。もしかしたら、今感じている体の不調が、病気を予防するための警告かもしれません。
目次
■その疲れ、実は「糖尿病のはじまり」かも?
糖尿病は、自覚症状が現れるまで気づきにくい病気です。「最近、なんだか疲れやすい」「喉が異常に乾く」「トイレが近くなった」といった症状が続いている場合は、糖尿病の初期症状かもしれません。早期に気づき、対策を取ることで、進行を防ぎましょう。
■糖尿病とは?放っておくと怖い“血糖の病”
糖尿病は、体内で血糖(血液中の糖)がうまくコントロールできなくなる病気です。インスリンというホルモンが血糖値を調節するのですが、これがうまく働かないと、血糖値が高いままになり、体のさまざまな器官に負担がかかります。
糖尿病は初期段階ではほとんど自覚症状がないため、気づかないまま進行することが多いのです。
◎1型糖尿病と2型糖尿病の違いとは
糖尿病には大きく分けて1型糖尿病と2型糖尿病の2つのタイプがあります。
-
1型糖尿病
主に若い人に見られます。これは膵臓がインスリンをほとんど作れなくなる病気で、インスリンの注射が必要です。
-
2型糖尿病
40歳を過ぎた中高年に多く見られ、食事や運動不足など生活習慣の影響を受けて発症します。こちらは生活習慣を見直すことで予防できることが多いです。
◎なぜ今、糖尿病が増えているのか?
現代社会では、食生活の乱れや運動不足が原因となり、糖尿病の発症が増加しています。糖尿病患者が年々増えており、健康診断で「糖尿病予備群」と言われた方も多いのではないでしょうか。
肥満やストレスも糖尿病を引き起こすリスクが高く、日常生活でのちょっとした心掛けが予防に繋がります。
■なぜ糖尿病になるのか?意外な“原因”に要注意
糖尿病が発症する原因は、遺伝や生活習慣、環境要因が絡み合っていることがほとんどです。原因を理解することで、予防や改善がしやすくなります。
◎「甘いものの食べすぎ」だけじゃない理由
糖尿病の原因として「甘いものの食べすぎ」がよく言われますが、実はそれだけではありません。
糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンがうまく働かなくなることが原因です。過食や運動不足、肥満、ストレス、さらには遺伝的要因も大きく関わっています。
◎あなたは大丈夫?2型糖尿病になりやすい人の特徴
特に2型糖尿病は、生活習慣が大きな要因となります。例えば、40歳を過ぎた方や、運動不足で肥満気味の方、家族に糖尿病の人がいる方などは、糖尿病のリスクが高いと言われています。自分の生活習慣を見直し、適切な食事と運動を心がけることが大切です。
◎1型糖尿病は“突然”やってくる ― 原因は自己免疫?
1型糖尿病は、主に若年層に多く、膵臓がインスリンを作れなくなる病気です。原因はまだ完全には解明されていませんが、免疫系が誤って膵臓の細胞を攻撃することが原因と考えられています。1型糖尿病は突然発症することがあり、発症後はインスリン注射が欠かせません。
■「まさか自分が…」糖尿病の初期症状はこうして始まる
糖尿病の初期症状はとても軽く、ほとんど気づかないことが多いです。しかし、進行すると体にさまざまな影響を与え、深刻な合併症を引き起こすこともあります。
◎気づかないうちに進行するサイレント疾患
初期段階ではほとんど自覚症状がありません。そのため、自分が糖尿病だと気づかずに病気が進行してしまうことがほとんどです。血糖値が高い状態が続くと、目や腎臓、神経にダメージを与え、最終的には深刻な合併症を引き起こすこともあります。
◎「喉の渇き・疲労・トイレが近い」はサインかも
初期症状として、喉が渇く、頻尿になる、体重が急に減少する、疲れが取れないなどがあります。
これらの症状は、血糖値が高くなることで体が脱水状態になり、エネルギーがうまく使えないために起こります。もしこれらの症状が続くようなら、早めに医師に相談することが重要です。
◎初期症状が出る“体のしくみ”
血糖値が高くなると、体は余分な糖分を尿として排出しようとします。そのため、トイレが近くなり、喉が渇く原因となるのです。また、細胞に糖分が取り込めなくなるため、エネルギー不足を感じて疲れやすくなり、体重が減少することもあります。
■どこからが“危険な数値”?糖尿病の検査と基準
糖尿病を早期に発見するためには、定期的な血糖値の測定が重要です。血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1c)の検査を受けることで、糖尿病やその予備軍かどうかを確認できます。
◎血糖値・HbA1c…何を見ればいい?
糖尿病の診断には、いくつかの基準があります。代表的なものとしては、「空腹時血糖値126mg/dL以上」「HbA1c6.5%以上」といった数値があります。もしこれらの数値が基準を超えていた場合、糖尿病の可能性があるため、早めに治療を受けることが大切です。
◎病院で行われる糖尿病の主な検査とは
糖尿病の検査では、血液検査(空腹時血糖、HbA1c)や尿検査(尿糖)を行います。これらの検査を通じて、糖尿病の状態を正確に把握し、必要な治療を開始します。また、糖尿病予備群と診断された場合は、生活習慣を見直すことが大切です。
◎「予備群」と言われたら何をすればいい?
糖尿病予備群と診断された場合、まだ糖尿病には至っていませんが、血糖値が正常範囲を超えている状態です。この段階で生活習慣を見直すことで、糖尿病の発症を防げます。食事に気をつけ、適度な運動をすることが予防には効果的です。
■糖尿病は“気づいた今”がはじまり
糖尿病は自覚症状がないうちに進行してしまいます。喉が渇く、疲れが取れないなどの軽い症状でも見逃さず、早期に検査を受けることが重要です。少しでも気になる症状があれば、まずはご相談ください。あなたの健康管理のお手伝いをします。
当院の生活習慣病の治療についてはこちら。